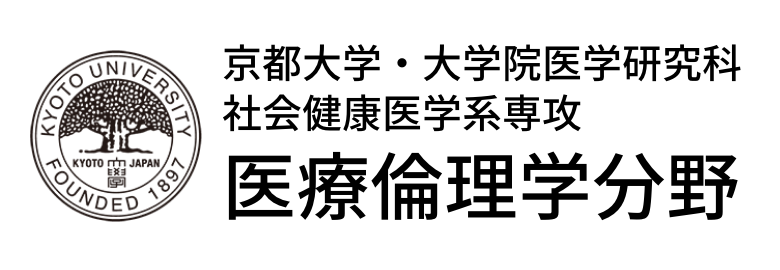死後脳研究は神経疾患や精神疾患の解明に重要な役割を果たしています。こうした研究活動には、研究参加に協力する人の存在が欠かせません。一方、日本では、解剖写真の SNS 投稿が大きな話題になったように、身体の取り扱いや流通のあり方について、多くの人々が関心を持っています。研究に参加する意思を表明した市⺠・患者の視点に寄り添い、その背景や関心をより深く知る作業が研究側にも求められると考え、調査をまとめました。
これまで、研究倫理の文脈でも、『遺体』や『死後』の話はほとんど議論されてきませんでした。今回いただいた反応からは、協力の意向の背景として「医学・研究に貢献したい」という思いが一番多く挙げられましたが、これが単一の背景というよりは、「受けた医療への感謝」「家族・周囲の影響」など、実際には複数の思いや動機が連なり、重なって表明に至っていることが多いようです。登録者の年齢・立場による違いもあるようでした。また、意思表明をした後も、研究の進展について継続的に関心を持ち続けていることがわかりました。
ご本人の関心や懸念に応じたコミュニケーションの重要性、家族向けガイダンスの充実や、研究成果の定期的な発信の重要性が明確になりました。死後の研究参加は人や他者を信頼し、そこに託す視点が強くなります。この視点は、ブレインバンクに限らず、現在・将来の研究活動にとって大きな広がりがある概念だと考えています。
Yusuke Inoue, Maki Obata, Maho Morishima, Shigeo Murayama, Yuko Saito (2025). Bridging minds: Participant perspectives on postmortem brain research and engagement. Neuropathology. https://doi.org/10.1111/neup.13030

報道関係
「ご遺体に学ぶ医療・医学研究を⽀えるもの―解剖・死後の⾝体提供を表明した⼈々52名の証⾔の検討―」
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2025-02-14-0
「解剖」(化学工業日報、1頁)2025年2月20日
「死後脳研究、ブレインバンクへの提供意思登録者に意向調査-京大ほか」(医療NEWS QLifePro)
https://www.qlifepro.com/news/20250227/brain-bank.html
死後の脳提供意思を表明した人々の想い 京都大学がヒアリング調査(大学ジャーナル)